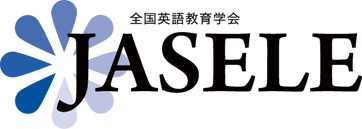|
(2025年7月収録) |
| 司会 |
今まで先生が携われたJASELEとKATEの企画で、思い出深いテーマには、どういうものがありますでしょうか? |
| 斉田 |
KATEの会長、大会実行委員長として、2019年度の神奈川研究大会を、横浜国立大学で開催したときのシンポジウムは、思い出深い内容でした。「英語教育における学習評価のあり方を考える―真に学習者が伸びる評価を目指してー」というテーマで、信州大学の酒井英樹先生、新潟大学でKATE の前会長で新潟大学の松沢伸二先生、大東文化大学の靜哲人先生の3名の先生方にご登壇をお願いし、非常に密度の濃い,ためになる内容をご発表いただきました。登壇者のお話にずっと聞き入ってしまって、コーディネーターであることをすっかり忘れてしまったくらいです。 |
| 斉田 |
全国英語教育学会第50回記念大会のシンポジウムでは、「日本の英語教育の将来―全国英語教育学会JASELE50年を総括し、未来を描くー」というテーマで、コーディネートと登壇者をお引き受けしました。非常に大きなテーマで、毎日このシンポジウムのことを考えながらすごしております。 |
| 司会 |
これはきっと、参加者の皆さんへの宿題にもなりますね。皆さんがこう持ち寄って、そこでこういう意見を交わされるといいような内容ですね。 |
| 斉田 |
皆さまが参加していただけるような企画にできたらいいなあと考えているところです。 |
| 司会 |
ありがとうございます。 学会というのは、おそらく未来を予言して、あるいは未来がこうなってほしいという気持ちを込めて、研究したり発表したりされている場だと思うのですが、先生ご自身が過去において未来予想したことを,実現なさったことはございますか? |
| 斉田 |
英語教育研究の世界に入ってきたのが25年前で,「公教育としての英語教育をどう改善していくのか」という点から、テストをどのように開発し、どのように評価を行い、どのように改善をしていくのかということが、私の中で継続して取り組んでいるテーマです。具体的には、IRTという測定道具を使って、大規模な公的なテストを分析したり開発したりして、英語教育改善のための示唆を得るといった研究をずっと行ってきました。学習指導要領を実施したその教育効果を国がきちんと測る必要があると考えておりましたが、25年前はまだ日本には全国学力調査はありませんでした。当時はアメリカの全米学力調査に注目をしていて研究をしたこともありました。こうした全国的な調査を、日本の公教育にも導入する必要があると、当時から主張しておりました。そういう中、日本でも2007年度から全国学力調査が実施されることになりました。当初英語は実施されていませんでしたが、英語も評価しようという動きが、2020年度の前ぐらいにあって、文部科学省の方々が,英語教育で測定分野の研究を行い、学力調査に関心がある研究者を探して、私の研究室を訪ねてこられました。まずは, IRTを使った英語力の経年比較分析調査の設計ができて、令和3年度に初めて実施されました。 さらに,悉皆調査である「全国学力・学習状況調査」の分析も行うようになり、今年度からIRTを導入した調査設計の下、学力の経年変化を明らかにする取り組みが,現実のものとなっています。令和8年度の英語からは、IRTが導入され、悉皆調査でも経年比較ができるテストが実際に実施されることになりました。 ちょうど25年前に描いていた未来が、令和8年度に実現することになります。 |
| 司会 |
素晴らしいですね。 どうしてもこの学会の中だけで通じることではなくて、こう学外の方も今のこの英語教育ってどうなっているのかということを理解する上で、やはりその調査結果やテスト結果を年代比較できるのは,今まであまりなかった画期的なことだと思います。このようなレールが引かれてきて、次の半世紀の願いというのはどのようなものございますか? |
| 斉田 |
半世紀は長いですが、1年1年積み上げてきて、今年,第50回記念大会に到達できたことは,大変意義深いことだと思います。英語教育がますます発展して、学会の会員数も増えて活性化していくというのは大変喜ばしいことです。様々な教科がある中でも、やはり英語は特別で、国際競争にさらされていることもあり、どの教科よりも研究活動が盛んで、先端を走っている教科といわれています。 研究と実践,実践と理論が融合・統合しながら発展していってほしいというのが願いです。先ほど申し上げたように、IRTによって英語力を評価して、経年変化を共通尺度上で示していくことができるようになるので、実践の効果が客観的に全国共通の尺度上で評価される時代になってくるだろうと予想しています。英語力は、世界基準で評価されるので、世間の関心が高くなるのは必然ですね。 だから、そういう変化していく世の中で、学会として研究力、実践力ともにいっそう高めていくこと,学会の社会貢献として、国の英語教育政策に関して助言や提案ができる,そうした社会貢献力がさらに発展していくこと,が私の願いです。 |
| 司会 |
ありがとうございます。 共通テストあるいは英検もそうでしょうけれども、以前のテストの問い方と違って、より国際標準に近づいてきているのではないかなというふうに思います。日本人の英語力というものをこう国際標準で比較すると、どうしても「日本の英語教員は何をやっているんだ」っていうふうになってしまって、がっかりしてしまうところもあると思うのですけれども、一方で、ガラパゴス化した日本の英語教育を世界に引っ張り出すには、今まで頑張ってきた現場の先生方を何か鼓舞できるような、「日本の英語教育はこんなにいいんだよ」ということを示すテストは、作られるのでしょうか? |
| 斉田 |
テストは、受ける人の可能性を引き出して伸ばしていくためにあるもので、解答するのが楽しいものじゃないといけないと思っています。まずは自分が教えている子供たち、生徒、学習者をよく見つめることだと思っています。子供1人1人が将来の日本を背負っていく,大事な存在で、1人1人の可能性を伸ばせるように、子供たちをよく見つめて、導いていくための研究を行って、その成果を子どもたちの成長に還元していくことで,明るい未来をつくっていってほしいと思っています。 自分の頭で考えて、何が良いことで何がいけないことなのかということをきっちりと判断できる子供たちを育て、今後、公正で民主的な社会をつくっていく担い手となってほしいと、そのための英語教育研究だなと思っているところです。 |
| 司会 |
ありがとうございます。 全人教育の中に英語教育を位置づけられて、また,英語教育研究においても,現場の子供たちがいかに成長し、楽しく学校生活を送れるかということを第一にお考えになるというのは,とても素晴らしい皆様へのメッセージになったのではないかと思います。 ありがとうございます。 |
| 斉田 |
どうもありがとうございました。 |