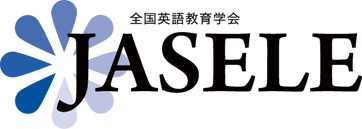大会プログラム紹介
シンポジウム
日本の英語教育の将来 ―全国英語教育学会(JASELE)50年を総括し、未来を描く―

斉田 智里
横浜国立大学、全国英語教育学会会長

深澤 清治
広島大学名誉教授、全国英語教育学会前会長・顧問

佐久間 康之
福島大学、全国英語教育学会 JASELE Journal 前編集委員長

森 好紳
白鴎大学、全国英語教育学会学生支援部部長
| 概要: |
もっと見る 本シンポジウムでは、全国英語教育学会の50年の歩みを振り返り、現在の研究動向を総括した上で、今後の方向性を議論する。前半では、『全国英語教育学会50周年史』をもとに本学会の発展を振り返り、学会誌JASELE Journal(旧ARELE)に掲載された研究を中心に日本の英語教育研究の動向を分析する。また、若手研究者支援の現状を紹介し、学会としての取り組みと今後の課題について検討する。 |
|---|
特別講演
AIとともに学ぶ時代の英語教育 ―日本全国の教育現場からのケーススタディ―

ELSA JAPAN合同会社 文教市場責任者
| 紹介: |
もっと見る特別講演概要: 本講演では、生成AIの登場という新たな教育環境の変化を踏まえ、日本の英語教育現場における実践的取り組みを考察する。現場の教員は、第二言語習得理論を踏まえた授業やICT活用、進学実績など、多様な要求に直面している。そうした状況下で、各教育現場ではAIの活用をどのように模索し、また向き合っているのか。本発表では、複数の教育現場から先進的な実践事例を取り上げ、AIとの共生時代における効果的な英語教育の在り方を探究する。各事例の分析を通じて、今後の英語教育におけるAI活用の可能性と課題を提示し、参加者からのご意見を頂戴したい。 特別講演講師 プロフィール: 慶應義塾大学・同大学院を卒業後、米ジョージア大学教育大学院にて授業デザイン法を学び、全米優等生協会に選出される。帰国後、聖学院中学・高等学校に英語教諭として勤務。2018年はオランダ・ユトレヒト大学大学院で認知心理学を研究。2016年度から2019年まで工学院中・高の教頭を務める。教育理論の知見に基づき、PBL (Project-Based Learning、問題解決学習) やアクティブ・ラーニングなど新たな授業スタイルを実践し続けている。2016年には日本人として初めてグロ−バルティーチャー賞の最終候補に選出される。秋田県湯沢市教育委員会や京都府京丹後市教育委員会のアドバイザー、日本私学教育研究所研究員などを兼任する。現在、東北大学医学系大学院で教育脳科学分野の博士論文と格闘中。著書に『世界で大活躍できる13歳からの学び』 (主婦と生活社、2006)。 |
|---|
課題研究フォーラム・授業研究フォーラム
課題研究フォーラム1年目
「生身からのことばで語る―AI時代の英語教師の成長―」 (関西英語教育学会)
| コーディネーター: | 山本 玲子 (京都外国語大学) |
|---|---|
| 提案者: |
|
| 指定討論者: | 吉田 真生 (京都大学大学院生) |
| 概要: |
もっと見る教師と学習者を人間的に動かすのは「生身からのことば」である。全身で感じる情動・思考を相手に届けるためにことばを選びそれを声に出す―そんな「生身からのことば」を感じた時,学習者は鼓舞され,教師は身を正す。本研究初年度のリサーチクエスチョン「教師は,いかに『生身の感覚』を教師の判断として信頼できるものにすることができるのか」は,「数値化できない『教師の感覚』をどこまで信頼してよいか」という現場の教師の葛藤の声がきっかけとなった。小学校教師 (英語専科) を対象としたインタビューの分析を通し,児童の変容を自らの省察に反映させ,いわば様々な仮説を同時並行的に更新し自分を刷新し続ける実践者の姿が見いだされた。 |
「『読むこと』を起点とした統合型言語活動の指導」 (四国英語教育学会)
| コーディネーター: | 池野 修 (愛媛大学) |
|---|---|
| 提案者: |
|
| 概要: |
もっと見る本課題研究フォーラムでは,「読むこと」を起点に,学習者が夢中になって取り組める授業づくりを探究する。具体的には,個別最適な学びと協働的な学びの両立を目指し,英文を読んでグループで話し合うリテラチャー・サークルなど,統合型言語活動を中心に据えた授業を展開する。学習者がICTやAIツールを活用し,単元内自由進度学習を取り入れ,読んだ内容を自分ごととして捉え,互いに考えや気持ちを伝え合える環境を整える。これにより,英語の知識・技能を高めるとともに,主体的・対話的な学びを促進する。また,中学校での実践研究を基盤に,小学校から高等学校までを連続的に接続する英語教育の在り方を模索する。さらに,多様な学び手に応じた指導法を取り入れ,学習者のエンゲージメントを促す授業設計に挑戦する。 |
「教室でできる英語語彙指導を考える」 (北海道英語教育学会)
| コーディネーター: | 笠原 究 (北海道教育大学) |
|---|---|
| 提案者: |
|
| 概要: |
もっと見る本フォーラムの目的は,日本の教室環境に適した語彙指導の在り方を,語彙研究や関連する研究領域の知見を援用しながら提案することにある。昨年度は,教員を対象とした調査などをもとに,語彙学習の目標を受容語彙と産出語彙の観点から検討した。2年目である今年度は,設定した目標を達成するための語彙指導について考える。具体的には,まず日本の指導環境における制約を踏まえた上での語彙指導の原則と方向性を示す。その上で,教科書やそれ以外の教材を用いて,どのように語彙を増やし,その知識を言語使用に結びつけていくかについての具体的な指導方法を提案する。フロアとの議論も通して語彙指導の目指すべき姿について考えていきたい。 |
「通常の学級での英語授業における学習者支援 ―持続可能な『個別最適な学び』の実現―」
(中国地区英語教育学会)
| コーディネーター: |
|
|---|---|
| 提案者: |
|
| 概要: |
もっと見る日本の英語教育において個別最適な学びが重視されるようになり,教員には英語学習に困難さを感じる児童生徒に対して細やかな支援を行うことが求められるようになっている。本フォーラム1年目であった昨年は,「国際交流活動」と「UDL (Universal Design for Learning) に基づく学習支援」を軸とした中学校,高等学校における中長期的な実践事例を紹介した。2年目である今年は,教員が過度な負担感を感じることなく同様の実践に取り組んでいくためには,どのような指導の工夫,ICTの活用が求められるのか,さらには教員養成においてそれらについての学びをどのように保障するのかについて提案する。通常の学級での英語学習において求められている「もはや特別ではない支援」についてフロアの皆さんとともに思索を深めたい。 |
「英語科の授業における生成AIの活用と課題」(東北英語教育学会)
| コーディネーター: | 丹藤 永也 (青森公立大学) |
|---|---|
| 提案者: |
|
| 概要: |
もっと見る生成AIの活用は学習者のモチベーションを高め,スキルの習得に役立つとされている。この生成AIを英語の授業に活用するメリットとしては,多様な学習コンテンツの提供やパフォーマンスに対する即時フィードバック等が可能となり,個別最適な学びをより推し進めることができる点が挙げられる。また,教材作成や採点等の教師の負担も軽減され,指導の質の改善も見込まれる。しかしながら,技術的・倫理的な課題も多く指摘されており,指導者は生成AIの特性を理解しながら,適切に活用する必要がある。本授業研究フォーラムでは,中学校,高校,大学の各校種での生成AIを活用した授業実践を通してその効果と課題を整理し,今後の英語科の授業における効果的な生成AIの活用について検討したい。 |
「中学校における読むことの『思考力、判断力、表現力等』の指導のポイント」
(中部地区英語教育学会)
| コーディネーター: | 酒井 英樹 (信州大学) |
|---|---|
| 提案者: |
|
| 概要: |
もっと見る平成29年告示の中学校学習指導要領において,外国語科の読むことについては,「ア 必要な情報を読み取ること」,「イ 概要を捉えること」,「ウ 要点を捉えること」ができるようにすることが求められるようになった。改訂後に実施された令和5年度全国学力・学習状況調査【中学校】英語において,それぞれに関連する読むことの問題に関する正答率は,36.7% (大問6),35.2% (大問7(2)),56.6% (大問8(1))であった。要点を捉える問題では5割を超えたものの,決して高くはなく,まだまだ課題が残っている。そこで,本フォーラムでは,中学校における読むことの「思考力,判断力,表現力等」の指導に焦点を当てて,何をどのように指導したら良いのか提案する。 |
大学生・大学院生フォーラム
1日目: 大学生・大学院生のための交流の場
| 司会: | 鈴木 健太郎 (北海道教育大学) |
|---|---|
| 概要: |
もっと見る本フォーラムは埼玉研究大会の2日間にわたってお昼に開催されます。 1日目は,参加者の皆さまでグループを作り,情報交換や交流をしていただく予定です。 |
2日目: 大学生・大学院生のためのキャリアパス ―若手大学教員のワークとライフ―
| 司会: | 小木曽 智子 (富山大学) |
|---|---|
| 登壇者: | 山内 優佳 (広島大学) |
| 概要: |
もっと見る本フォーラムは埼玉研究大会の2日間にわたってお昼に開催されます。2日目は,若手の先生をお招きし,現職に至るまでの体験談や実際に就職して感じたことなどを伺いながら,英語教師・研究者のキャリアパスについて考えを深めていきます。 |
ワークショップ
1. 「Learning by Storytelling (LBS) 指導法のWorkshop」

小野 尚美
成蹊大学

田縁 眞弓
京都光華女子大学
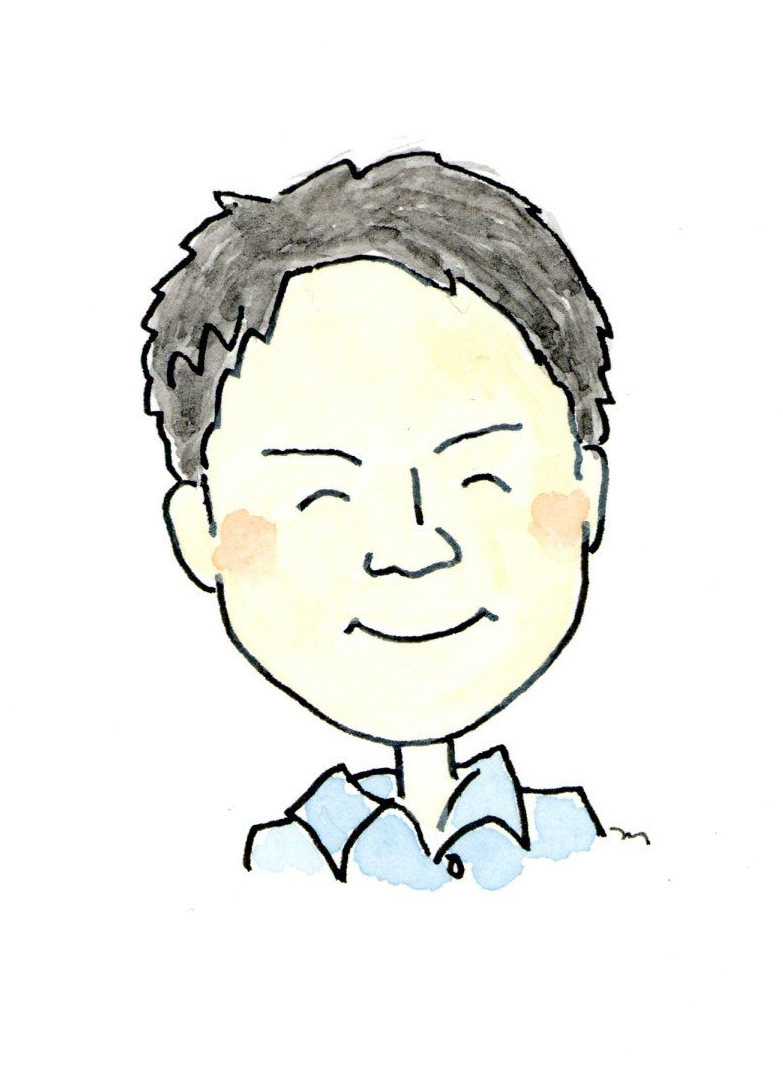
吉本 連
うつほの杜学園 講師、元ノートルダム学院小学校

赤枝 康隆
明石市立魚住中学校
もっと見る
ここでは、8年前から開発を続けている英語絵本を活用した小学校英語のためのLBS指導法の実践を行う。この指導法は 1)インタラクション、2)場面の並べ替え活動、3) 場面のリテリング、4) 英語による発信活動から成っている。児童の既習の知識を活用し、絵本が提供する状況の中で英語によるインプットから徐々にアウトプットできるように導く。また、授業ごとに学習についての振り返りを書かせ、児童の英語学習への動機を高める。4番目の活動では、英語力の違いに考慮し、各学年に適した活動が入る。今回は、研究会が独自で作成した絵本を使った高学年の実践、中学年のオリジナルページ作成、公立小学校で行った低学年の実践を紹介する。
2.「生成AIの活用」

青田 庄真
茨城大学
もっと見る
このワークショップでは、英語の授業における生成AIの具体的な活用方法やアイデアを体験し、学ぶことを目的としています。主な対象者は、ChatGPTを試してみたものの継続的な使用には至らなかった方や、なんとなく敬遠してきた方など、初級~中級の利用者です。この1年ほどの間にも、AIの精度自体が向上したことはもちろん、様々な機能が無料で簡単に利用できるようになっています。このワークショップでは、英語教師として日常の教育活動や自己研鑽に役立つ機能をご紹介し、具体的な場面を想定した練習課題に参加者ご自身の端末で取り組みながら、体験的に学んでいただきます。なお、本ワークショップではChatGPT以外の生成AIも取り上げますが、無料で利用可能なサービスのみを扱います。
3.「ディスカッションの指導」

上山 晋平
福山市立福山中・高等学校
もっと見る
「トリオ・ディスカッション」(通称:トリディス)は、3人・3分間で行うポイント制の即興ディスカッション。中学生や高校生でも無理なく取り組め、教師の負担もほとんどありません。「添削ほぼナシ作戦」で、話す力と書く力を同時に伸ばせるのも大きな特長です。全県導入された青森県をはじめ、全国に広がる中、“Let me go first!”と声をそろえる生徒の姿に、活動の効果を実感する声が多数寄せられています。本ワークショップでは、ディスカッションの進め方や評価方法、今どきの生徒の学びを引き出すポイントなど、忙しい現場ですぐに役立つ具体的な工夫をご紹介します。
地区特別企画: 関東甲信越英語教育学会 (KATE) 50年の歩み
来年,KATEも学会設立50周年を迎えます。そこて,地区特別企画として,JASELEの皆様とともに歩んできたこの50年のKATEの取組みを振り返リ,それぞれの時代において,どういった目的や思いを抱きながら,学会活動を進めてきたのかを傍観してみたいと思います。
常に英語教育に真摯に取リ組んできた KATEの姿勢をお感じいただければ幸いです。きっと,一つ一つの学会活動に込められた思いには,全国各地区の英語教育関係者の皆さまにも同感していただけることも多くあろうと願っております。
企画内容と地区特別企画ページは以下の通りになっております。
企画1
1977年から現在に至るまで121号発行されてきました 「KATE Newsletter」を紐解き,4つの年代に分けて,その時々でKATEが英語教育にどう向き合ってきたのかを振り返ります。担当者は以下の通りです。 (欠番除く)
- (1) 1977年~1985年 飯島睦美 (群馬大学)
- (2) 1986年~1993年 伊藤 扇 (慶応義塾幼稚舎,東京学芸大学連合大学院)
- (3) 2002年~2011年 栗原達也 (桐朋中学校・高等学校,東京学芸大学連合大学院) [New]
- (4) 2012年~2024年 早房拓実 (筑波大学大学院) [New]
企画2
歴代のKATE会長ヘインタビューをさせていただき,英語教育への熱い思いを語っていただきました。担当者は以下の通りとなっております。
- ・山本昭夫 (学習院高等科)
- ・物井真一 (筑波大学附属高等学校)

金谷憲 先生
2002年度 ~ 2005年度 KATE会長
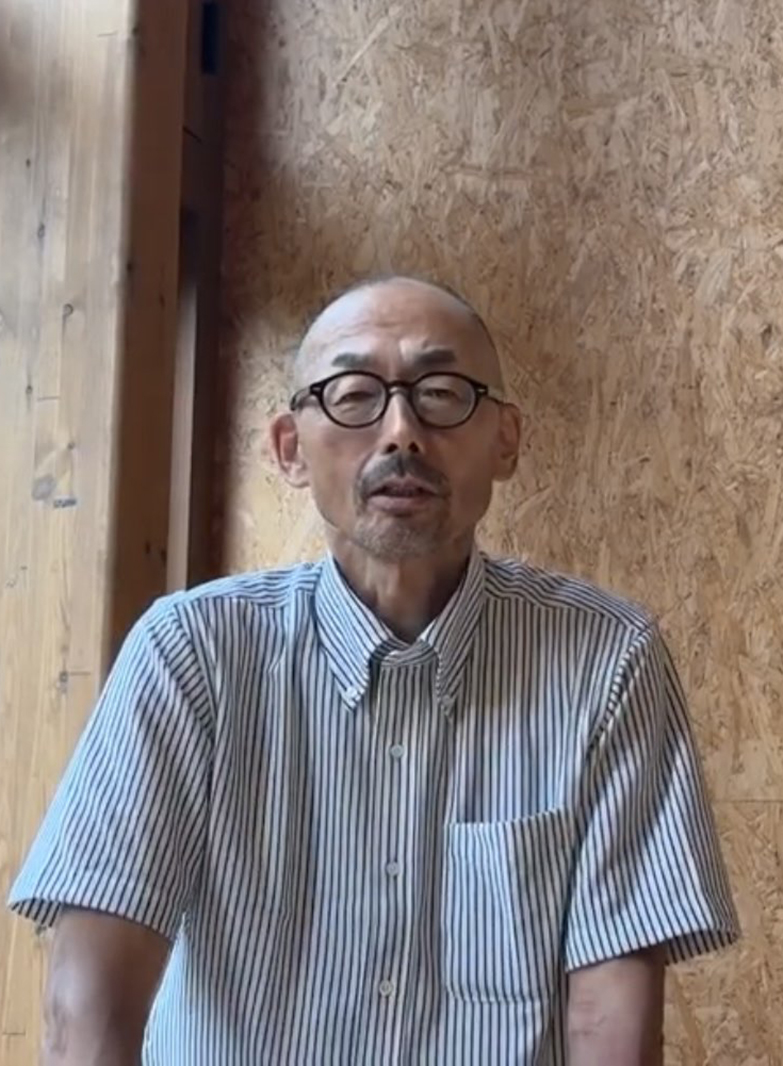
卯城祐司 先生
2010年度 ~ 2013年度 KATE会長
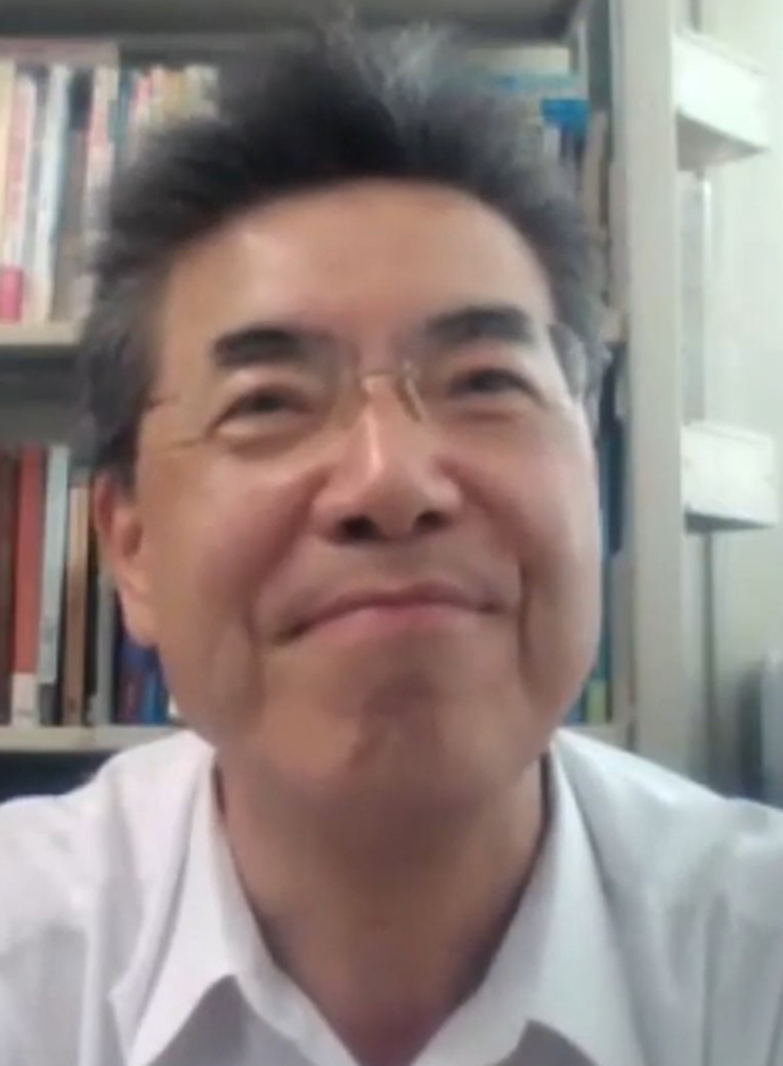
松沢伸二 先生
2014年度 ~ 2017年度 KATE会長

斉田智里 先生
2018年度 ~ 2021年度 KATE会長